アロリエクリニックさま|クリニックの開業は「婦人科診療に『栄養』の視点を取り入れるため」
不調の改善は胃腸のケアから――原点への立ち返りに加えた「栄養療法」という新たな選択肢

はじめに
これまでの治療では解決が難しかった疾患や症状に対して、「オーソモレキュラー栄養療法」を新たなアプローチとして導入する医師が増えています。本記事では、実際に栄養療法を取り入れている医療現場の声をお届けします。
今回は、栄養療法を積極的に導入している「アロリエクリニック」の市川 りえ先生に、株式会社MSSクリニック・サポート部の河嶋 健太がお話を伺いました。投薬による診療をはじめとした既存の診療方法に疑問を感じ、「胃腸から体を整える」という原点に立ち返り、栄養療法を取り入れた診療を行うためにクリニックを開業された市川先生。婦人科における栄養療法の実践についてご紹介します。詳しくは、ぜひ下記の本編をご覧ください。
1. 胃腸から整える――原点に立ち返った診療を実践するための開業
河嶋:まずは栄養療法を診療に取り入れたきっかけや背景、また、ご開業に至った経緯について教えていただけますか。
市川:保険診療だけでは“治療が行き届いていない”と感じる患者さんが一定数おり、根本から体の調子を整える必要があると考え、栄養療法の視点を取り入れ始めました。
前の職場では短時間で特定の処方を繰り返すスタイルが基本でしたが、血液検査データで気になる点を患者さんにお伝えしていったんです。すると、一人にかける時間が自然と増え、私の外来に患者さんが集中することがあり、他の先生方から「栄養の話はしないでほしい」と言われてしまったんです。
そういったこともあり、「必要だと思えない処方はもうしたくない」という思いも強くなったので、さまざまな検査データの数値を読み取り、“まず胃腸から整える“という原点に立ち返った診療を自分の責任で実践するため、開業することにしました。
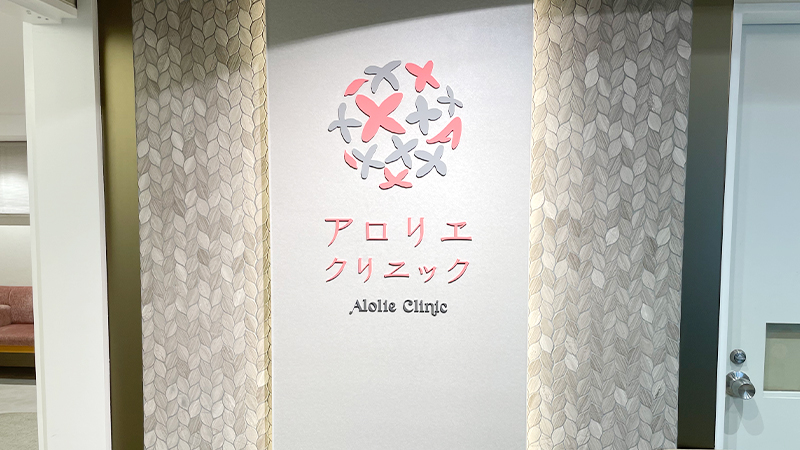
2. 「保険診療の範囲」で行える治療に感じた限界
河嶋:「保険診療の範囲」で行う診療で感じる難しさとは、具体的にはどういったケースがありますでしょうか。
市川:例えば、もともと胃腸が弱く、“食べても消化・吸収されにくい”患者さんです。特に女性に多い印象ですね。保険で行える治療では難しいと感じています。そのような患者さんに栄養療法を行っています。状態を詳しく把握するために、ピロリ菌やタンパク質、ビタミンDなどを評価する検査を行います。そうした結果から、まずは患者さんの栄養状態を把握して、投薬を含めた、必要に応じたアプローチを検討します。消化・吸収の状態が悪ければ薬の体感も得にくいので、いろいろな治療をしてきたけれどなかなか良くならないとお困りの患者さんには、胃腸のケアから入ることが多いですね。
3. 栄養療法の実践でみえた、婦人科領域の不調パターン
河嶋:婦人科のご診療に栄養療法を取り入れていらっしゃいますが、患者さまにはどのような傾向がみられますでしょうか。
市川:若い世代の不調で多いのは、やはりPMS(月経前症候群 )や生理痛ですね。実は、こうした患者さんたちの血液検査データは同じようになることが多いんです。栄養不足、低コレステロール、血糖値の乱れ……このパターンに尽きる、といっても過言ではありません。それぞれの状態に合わせて必要な栄養素やアプローチのご提案はしていますが、どうしても自費診療になってしまうので、若い世代の患者さんは金銭的に継続が難しいところもあります。ですが、例えば、いわゆる“更年期”と言われるライフステージの患者さんなどは、「更年期症状」だと思っていたことが、検査によって、実は「血糖コントロールの問題」だったと分かることもあり、比較的前向きに栄養療法によるアプローチを取り入れてくださる印象です。

4. 栄養療法が患者さまに与える「納得感」
河嶋:栄養療法に取り組んだ患者さまの反応はいかがでしょうか。
市川:既存の診療だけでなく、栄養療法の視点を加えた診療を行ったことで、ご本人の「納得」につながる場面が増えたと感じています。「特定のホルモンの問題だと思って受診したけれど、検査では明確な異常はなく、栄養の問題だったと分かったので良かった」、「栄養を補う取り組みを数カ月続けて、体が楽になったと感じた」など、「ここに来て良かった!」といったお声をいただきますね。
特に印象に残っているのは、若い女性の患者さんで、不安感が強く、検査や診察を頻回希望されていた方がいました。血液検査データから、不足が疑われる栄養素をしっかりと補い整えていくと、次第に受診間隔が落ち着き、久しぶりに受診された際には表情がとても穏やかに見えました。ご家族からも「性格が柔らかくなったみたい」との言葉があったと伺っています。
5. スタッフさまの採用は「診療方針に共感してくれた方を」
河嶋:スタッフのみなさまの協力体制や、栄養療法への理解の深め方について教えていただけますか。
市川:スタッフには、開業当初から「栄養で根本から整える」という診療方針を共有しています。栄養療法を学んでいる助産師を採用したので、他のスタッフも当院の方針やその影響を受けて勉強会に参加したり、MSSさんが提供している無料動画で学習したりしていますね。
あとは、半年に一度ほどスタッフも血液検査を行って、みんなで「どこが足りないか」を数値で確認します。スタッフにも必要な栄養素を摂ってもらえるよう、サポート体制を取っています。

6. これからの医学教育には「栄養」の視点が加わってほしい
河嶋:先生は今後、栄養療法はどのようになってほしいとお考えでしょうか。
市川:そもそも論として、医学部は地域医療を支える「地域枠」や、地域医療についての講義をもっと増やすべきだと考えています。そうすることで、「志」をもった医師が増え、投薬一辺倒の診療が変わり、診療方法にも多くの選択肢も生まれると思うからです。そのためにも、医学部で、栄養についての講義が当たり前になると良いですね。もちろん、薬が必要な局面もありますが、「まずは栄養状態を整える」という選択肢があることを知っていれば、志をもつ医師によって、患者さんの選択肢も広がるはずだと思います。
栄養療法の導入をご検討中の医師の方へ
現在行っているご診療に栄養療法という新たなアプローチを加え、患者さまの納得感、満足度をアップさせませんか。
当社では、医療機関で栄養療法の導入を検討されている先生方に向けたサポートを、多数ご用意しております。臨床現場での導入事例や患者さまの変化など、より具体的な情報も共有しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
無料相談・勉強会のご案内
MSSのプロフェッショナルが、栄養療法の導入・運営に関する無料相談を承ります。また、スタッフさま向けに無料勉強会を開催し、栄養療法についての知識向上や診療での実践に役立つ情報もお伝えします。無料相談・勉強会にご興味のある先生はこちらからお申し込みください。
無料登録のご案内
当社では、無料登録していただいた医療機関様、先生へ栄養療法導入をサポートする資料やセミナーを無料(一部セミナーは有料)でご提供しております。ご興味のある先生はこちらから無料でご登録いただけます。

 無料登録
無料登録